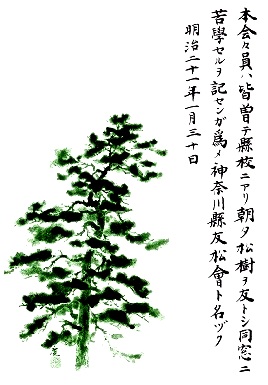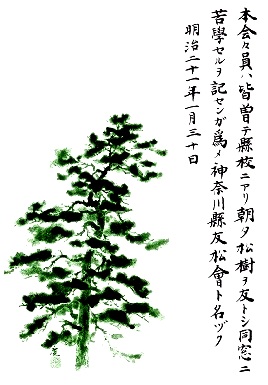友松会について
改めて、できることから着実に 会誌「友松」114号 巻頭言
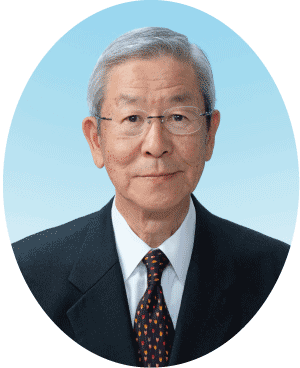
友松会 会長 小島 勝
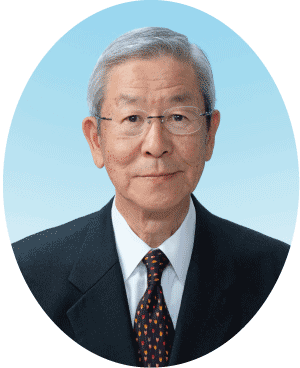
友松会 会長 小島 勝
本年、私たちの母校横浜国立大学は創基150周年、開学75周年を迎えました。1874年(明治7年)に神奈川県内に設置された小学校教員養成所(後の師範学校)を起源としており、まさに教育学部の創基150周年にあたります。11月9日に記念式典が、翌10日に横国Dayが開催予定です。今年の横国Dayでは恒例の「豊かな教育を考える会」を150周年にちなみ、研修部が中心となり「目の前の子どもがすこやかに育つために、今、私たちができること」をテーマにシンポジウムの準備を鋭意進めております。現職並びに退職された会員、そして学生会員の皆様、それぞれの経験と子どもたちへの熱い思いを持ち寄って実り多い会にいたしましょう。
すでにご案内のように、この150周年を迎えるにあたり、記念募金事業が計画され教育学部では学生歌「みはるかす」の歌碑を建立予定です。友松会は今年寄付をいたす計画です。皆様のご支援を重ねてお願いいたします。
昨年度より「研究奨励金」の運営規定が改定され、支部の諸活動や会員の教育研究に関わる活動の活性化を図るために有効に活用できるようになりました。昨年度は、初年度ということもあってか2支部と2団体からの申請にとどまりましたが、本年度は、支部活動をはじめ個人やグループの教育に関わる研究の活性化・推進のために是非ご活用ください。
コロナ禍の影響により2年間全支部で中止となっていた支部総会が復活してきました。昨年度は、6月10日の藤沢支部を皮切りに、2月の西・中支部まで14支部で、ブロック総会も川崎と横浜で開催されました。内容も総会だけでなく、研修会や講演会、懇親会等を兼ねて工夫されていました。本年度はより多くの支部やブロックで総会を開催し、会員相互の親睦と資質の向上を図っていただけたらと存じます。
支部総会が、世代を超えた各支部所属の教員中心の会であることに対して、同期会は教員以外の道に進んだ同期の会員も含めた会です。そして、この同期会の活動がなければ、教職につかない卒業生が半数以上を占める現状では友松会活動の充実は望めません。しかし、時代の流れか、この10年間、同期会開催の情報はありません。ただ、幸いなことにゼミ単位や科単位の会、恩師を囲む会のような「小さな同期会」はかなり開催されているようです。そこで、現状の同期会及び世話人会のあり方を見直し、これからの時代にふさわしい「同期会」を求めていきたいと思います。また、会員同士が互いの消息を確認でき連絡を取り合えるように、現在本部に保管してある会員名簿を整理し使い勝手のよい名簿を作成したらどうかという声があがっています。今後、皆様の声もいただいて検討してまいります。
2015年(平成27年)に始まった学生会員制度は、発足以来今年で満10年目を迎えました。この制度は、卒業生の大半が県下の教育界に就職せず、教職以外の職に就いたり県外の学校に勤めたりする状況から生まれたものです。入学時に入会し、在学中から友松会の諸活動に参加して友松会会員としての意識をもってほしいという思いからできた制度です。現在学生会員に直接関わる事業としては、教育実習の事前指導や教員採用試験の面接指導、学生ボランティア活動への支援等を行っています。また、横国Dayの「豊かな教育を考える会」でも学生会員の協力も得て実施しています。学生会員制度10年を期して、新たな支援や連携のあり方を改めて求めていきたいと考えます。
創基150周年の年、大学ではこの4月より教育学部長が木村昌彦教授から鈴木俊彰教授に引き継がれました。木村学部長には2期4年間にわたり友松会活動に対し温かいご支援を賜り心より感謝申しあげます。そして、鈴木新学部長には新たな視点で友松会を支えていただけたら幸いです。
本年度、現役員は任期最後の年を迎えました。この2年間に高め合ってきた同窓意識をエネルギーとして、改めてできることから一つずつ着実に取り組んでいく所存です。皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。
すでにご案内のように、この150周年を迎えるにあたり、記念募金事業が計画され教育学部では学生歌「みはるかす」の歌碑を建立予定です。友松会は今年寄付をいたす計画です。皆様のご支援を重ねてお願いいたします。
昨年度より「研究奨励金」の運営規定が改定され、支部の諸活動や会員の教育研究に関わる活動の活性化を図るために有効に活用できるようになりました。昨年度は、初年度ということもあってか2支部と2団体からの申請にとどまりましたが、本年度は、支部活動をはじめ個人やグループの教育に関わる研究の活性化・推進のために是非ご活用ください。
コロナ禍の影響により2年間全支部で中止となっていた支部総会が復活してきました。昨年度は、6月10日の藤沢支部を皮切りに、2月の西・中支部まで14支部で、ブロック総会も川崎と横浜で開催されました。内容も総会だけでなく、研修会や講演会、懇親会等を兼ねて工夫されていました。本年度はより多くの支部やブロックで総会を開催し、会員相互の親睦と資質の向上を図っていただけたらと存じます。
支部総会が、世代を超えた各支部所属の教員中心の会であることに対して、同期会は教員以外の道に進んだ同期の会員も含めた会です。そして、この同期会の活動がなければ、教職につかない卒業生が半数以上を占める現状では友松会活動の充実は望めません。しかし、時代の流れか、この10年間、同期会開催の情報はありません。ただ、幸いなことにゼミ単位や科単位の会、恩師を囲む会のような「小さな同期会」はかなり開催されているようです。そこで、現状の同期会及び世話人会のあり方を見直し、これからの時代にふさわしい「同期会」を求めていきたいと思います。また、会員同士が互いの消息を確認でき連絡を取り合えるように、現在本部に保管してある会員名簿を整理し使い勝手のよい名簿を作成したらどうかという声があがっています。今後、皆様の声もいただいて検討してまいります。
2015年(平成27年)に始まった学生会員制度は、発足以来今年で満10年目を迎えました。この制度は、卒業生の大半が県下の教育界に就職せず、教職以外の職に就いたり県外の学校に勤めたりする状況から生まれたものです。入学時に入会し、在学中から友松会の諸活動に参加して友松会会員としての意識をもってほしいという思いからできた制度です。現在学生会員に直接関わる事業としては、教育実習の事前指導や教員採用試験の面接指導、学生ボランティア活動への支援等を行っています。また、横国Dayの「豊かな教育を考える会」でも学生会員の協力も得て実施しています。学生会員制度10年を期して、新たな支援や連携のあり方を改めて求めていきたいと考えます。
創基150周年の年、大学ではこの4月より教育学部長が木村昌彦教授から鈴木俊彰教授に引き継がれました。木村学部長には2期4年間にわたり友松会活動に対し温かいご支援を賜り心より感謝申しあげます。そして、鈴木新学部長には新たな視点で友松会を支えていただけたら幸いです。
本年度、現役員は任期最後の年を迎えました。この2年間に高め合ってきた同窓意識をエネルギーとして、改めてできることから一つずつ着実に取り組んでいく所存です。皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。
「常盤台遺跡」とESD
 横浜国立大学学長 梅原 出
横浜国立大学学長 梅原 出
1974年、教育学部は本学で最も早く常盤台へキャンパスを移転しました。当時、教育学部の建物以外はなく、他の学部の校舎建築や周辺の環境整備が行われていたそうです。そのさなか、キャンパス内に遺跡が眠っていることが発見されます。ご存知の方も多いと思いますが、教育学部の菊地康明教授、岡本勇講師をはじめ史学専攻の学生等がこの遺跡の調査研究を進め、多数の土器や石器を発掘し、縄文時代の貴重な遺跡であることを明らかにしています。教育学部には、この「常盤台遺跡」保護に尽力してきた歴史があるのです。
この遺跡は、「帷子貝塚」として知られていたそうです。横浜国立大学『常盤台遺跡』(1982年)には、縄文時代中期にここに集落が存在したことが確実であると記されています。その後一度貝塚がなくなる期間を経て、縄文時代後期には再度貝塚群が形成されたということも報告されています。この変遷は小海進という環境の変化が作用したと考えられるそうで、この時期の常盤台は海が身近な存在であったことを示しています。現在のキャンパスからは思いもよらない古代人類の生活跡を感じられます。こんなに貴重なことがあるでしょうか。
現在、教育学部の多和田雅保教授、堀内かおる教授が中心となり、他分野の教員や学生が遺跡を活用した教育研究を行う場をつくり、人間と自然の関係を見通す契機としてESD教育と関連づけようという機運が高まっています。この遺跡が多くの方々に知っていただけるような企画も進めています。
本学は「ユネスコチェア」に採択され、「生物圏保存地域を活用した持続可能な社会のための教育」というプログラムを始めています。ESD教育の一環として教育学部でも熱心に取組まれています。歴史ある教育学部にしかできない取組が、どんどん広がっています。ぜひ友松会の皆様にも応援いただければと思います。
 横浜国立大学学長 梅原 出
横浜国立大学学長 梅原 出 1974年、教育学部は本学で最も早く常盤台へキャンパスを移転しました。当時、教育学部の建物以外はなく、他の学部の校舎建築や周辺の環境整備が行われていたそうです。そのさなか、キャンパス内に遺跡が眠っていることが発見されます。ご存知の方も多いと思いますが、教育学部の菊地康明教授、岡本勇講師をはじめ史学専攻の学生等がこの遺跡の調査研究を進め、多数の土器や石器を発掘し、縄文時代の貴重な遺跡であることを明らかにしています。教育学部には、この「常盤台遺跡」保護に尽力してきた歴史があるのです。
この遺跡は、「帷子貝塚」として知られていたそうです。横浜国立大学『常盤台遺跡』(1982年)には、縄文時代中期にここに集落が存在したことが確実であると記されています。その後一度貝塚がなくなる期間を経て、縄文時代後期には再度貝塚群が形成されたということも報告されています。この変遷は小海進という環境の変化が作用したと考えられるそうで、この時期の常盤台は海が身近な存在であったことを示しています。現在のキャンパスからは思いもよらない古代人類の生活跡を感じられます。こんなに貴重なことがあるでしょうか。
現在、教育学部の多和田雅保教授、堀内かおる教授が中心となり、他分野の教員や学生が遺跡を活用した教育研究を行う場をつくり、人間と自然の関係を見通す契機としてESD教育と関連づけようという機運が高まっています。この遺跡が多くの方々に知っていただけるような企画も進めています。
本学は「ユネスコチェア」に採択され、「生物圏保存地域を活用した持続可能な社会のための教育」というプログラムを始めています。ESD教育の一環として教育学部でも熱心に取組まれています。歴史ある教育学部にしかできない取組が、どんどん広がっています。ぜひ友松会の皆様にも応援いただければと思います。
友松会の皆様へ

横浜国立大学 教育学部長・教育研究科長 友松会名誉会長 鈴木 俊彰
友松会の皆様には、本学教育学部・教育学研究科の学生の教育・研究にご支援をいただき、誠にありがとうございます。
教育学部は、皆様もご存じのとおり、教員就職率の低迷という大きな問題を抱えております。その対策の一つとして、教員志望のより強い学生を入学させるため、令和4年度より教職志望の高校生向けの公開講座を開講しておりますが、教科横断的な講座が特徴の一つとなっています。
☆ 高校生から始める生物文化多様性~生物編~理科(植物学)×美術(木工芸)
☆ 高校生から始める生物文化多様性~文化編~国語(漢詩)×美術(浮世絵)
☆ 図工再体験~光を体験して図工の学びを考える/理科再体験~光を実験して理科の学びを考える
☆ 図工再体験 モノに命をふきこもう~アニメーション表現の面白さを体験しよう/映像と言葉の教育~アニメーションを分解し、再構成する
また、在学生に対しては、教育ボランティアや「わくわくサタデー」、「がやっこ探検隊」の活動を推奨・支援しているところですが、一昨年の横国Day「豊かな教育を考える会」シンポジウム~教育ボランティアの今、そして私たち~に学生も参加させていただき、様々なご助言をいただけましたことは、学生にとっても大きなプラスとなりました。
友松会の皆様におかれましては、毎年、教育実習事前指導や教採対策講座等におきましてご指導いただき誠にありがとうございます。4年間の学修を通して、一人でも多くの学校教員を養成していきたいと思います。引き続きご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
一方、友松会におかれましては、近年の卒業生の総会等への参加が少なく、気にかかっているところです。教育学部としても参加者数の増加に向けて積極的に協力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

横浜国立大学 教育学部長・教育研究科長 友松会名誉会長 鈴木 俊彰
友松会の皆様には、本学教育学部・教育学研究科の学生の教育・研究にご支援をいただき、誠にありがとうございます。
教育学部は、皆様もご存じのとおり、教員就職率の低迷という大きな問題を抱えております。その対策の一つとして、教員志望のより強い学生を入学させるため、令和4年度より教職志望の高校生向けの公開講座を開講しておりますが、教科横断的な講座が特徴の一つとなっています。
☆ 高校生から始める生物文化多様性~生物編~理科(植物学)×美術(木工芸)
☆ 高校生から始める生物文化多様性~文化編~国語(漢詩)×美術(浮世絵)
☆ 図工再体験~光を体験して図工の学びを考える/理科再体験~光を実験して理科の学びを考える
☆ 図工再体験 モノに命をふきこもう~アニメーション表現の面白さを体験しよう/映像と言葉の教育~アニメーションを分解し、再構成する
また、在学生に対しては、教育ボランティアや「わくわくサタデー」、「がやっこ探検隊」の活動を推奨・支援しているところですが、一昨年の横国Day「豊かな教育を考える会」シンポジウム~教育ボランティアの今、そして私たち~に学生も参加させていただき、様々なご助言をいただけましたことは、学生にとっても大きなプラスとなりました。
友松会の皆様におかれましては、毎年、教育実習事前指導や教採対策講座等におきましてご指導いただき誠にありがとうございます。4年間の学修を通して、一人でも多くの学校教員を養成していきたいと思います。引き続きご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
一方、友松会におかれましては、近年の卒業生の総会等への参加が少なく、気にかかっているところです。教育学部としても参加者数の増加に向けて積極的に協力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本 部 活 動
各部が分担した業務を中心に活動し、(本部活動として)協力して事業を推進しています。
(1) 総務部
友松会百三十余年の灯を継続、発展させるためにも会員相互の意識の昂揚と結束が求められています。
1.諸会議の企画運営と効率化
2.母校との連携と情報入手
3.各部会相互の連絡調整 新春のつどい等、親睦の会の企画運営
4.活動の基本になる会則、規則、細則等の見直し、など会の円滑な運営に心がけ、活性化を計っています。
(2) 経理部
主たる分担業務は、本部の経理事務、年度予算・決算を担当しています。
そのため事務局と常時連携を図り、会の運営の円滑化に務めています。
部会で課題の検討を図るほか、会費の納入状況の確認ならびに支出状況の把握等、会計整理の活動を行っています。
特に、年度予算案の立案と決算に関する活動は、会の活性化や発展を図る意味でも重要な会務と考えています。
(3) 弘報部
○会誌「友松」の発行
主な業務として、友松会会誌「友松」の編集・発行・発送を行っています。
友松会会誌「友松」はA4版で、毎年6月に発行を予定しています。
○会誌の主な内容
大学教授の寄稿、会員の教育論考、人生についての考え方等を軸に構成しています。
また、「豊かな教育を考える会」(研究・研修)報告、「松沢研究奨励賞受賞者」研究論文、 同期会報告、支部だより等の会員相互の情報、 総会、新春のつどいの報告、各年度の会務会計報告、会員の消息、組織名簿等を掲載し、豊かな会誌にするよう努力しています。
・HPの内容充実と更新
行事日程、諸会議の概要報告、友松だより等を掲載し、会の概要を掲載しています。
(4) 研修部
会員の研修を深めるため、次の業務を中心に活動しています。
1.松沢研究奨励賞受賞者の選考
研究奨励基金は、本会の元顧問・ 相沢義雄氏 (大正13年卒)が、叔父の松沢高次郎氏(明治13年卒)の遺志を顕彰するために寄付された基金、 吉田太郎氏、水戸部正男氏、大浦美代氏の寄付金を充てています。
昭和41年より実施。対象は会員の個人、または会員を中心とした団体としています。
受賞者には、賞状と記念品を贈呈しています。
2.豊かな教育を考える会の企画と運営
松沢研究奨励賞の受賞者を囲んで、教育の課題や諸問題について考え語り合う会を、横国Dayに合わせて実施し、神奈川の教育の充実進展に寄与しています。2019年度には「これからの教師を語る」のテーマでシンポジウムを行いました。
3.学生の就職支援
大学と連携し、就職支援活動として「教員採用試験直前面接対策講座」等を実施しています。(2020年度は中止)
(5) 組織部
県下45支部の現職 (校内)会員と、退職(校外)会員が支部長を中心に支部役員会を構成し、 支部の活動を展開していますが、組織はその活動を支援し組織強化につなげています。
会員名簿を作成し、会員個々の情報を本部に集約し、コンピュータに入力データー化しています。
それにより、全会員と本部との連繋を図っています。
支 部 活 動
県下(東京を含む)45支部の組織による、会員相互の情報交流や親睦を図ることを中心にした支部活動を行っています。
活動の様子は「支部レポート」参照)
同 期 会 活 動
卒業時に同期会を組織、世話役を中心とした情報交流や親睦を図る活動です。
◎未組織の「期」は1日も早い組織化が期待されています。
各部が分担した業務を中心に活動し、(本部活動として)協力して事業を推進しています。
(1) 総務部
友松会百三十余年の灯を継続、発展させるためにも会員相互の意識の昂揚と結束が求められています。
1.諸会議の企画運営と効率化
2.母校との連携と情報入手
3.各部会相互の連絡調整 新春のつどい等、親睦の会の企画運営
4.活動の基本になる会則、規則、細則等の見直し、など会の円滑な運営に心がけ、活性化を計っています。
(2) 経理部
主たる分担業務は、本部の経理事務、年度予算・決算を担当しています。
そのため事務局と常時連携を図り、会の運営の円滑化に務めています。
部会で課題の検討を図るほか、会費の納入状況の確認ならびに支出状況の把握等、会計整理の活動を行っています。
特に、年度予算案の立案と決算に関する活動は、会の活性化や発展を図る意味でも重要な会務と考えています。
(3) 弘報部
○会誌「友松」の発行
主な業務として、友松会会誌「友松」の編集・発行・発送を行っています。
友松会会誌「友松」はA4版で、毎年6月に発行を予定しています。
○会誌の主な内容
大学教授の寄稿、会員の教育論考、人生についての考え方等を軸に構成しています。
また、「豊かな教育を考える会」(研究・研修)報告、「松沢研究奨励賞受賞者」研究論文、 同期会報告、支部だより等の会員相互の情報、 総会、新春のつどいの報告、各年度の会務会計報告、会員の消息、組織名簿等を掲載し、豊かな会誌にするよう努力しています。
・HPの内容充実と更新
行事日程、諸会議の概要報告、友松だより等を掲載し、会の概要を掲載しています。
(4) 研修部
会員の研修を深めるため、次の業務を中心に活動しています。
1.松沢研究奨励賞受賞者の選考
研究奨励基金は、本会の元顧問・ 相沢義雄氏 (大正13年卒)が、叔父の松沢高次郎氏(明治13年卒)の遺志を顕彰するために寄付された基金、 吉田太郎氏、水戸部正男氏、大浦美代氏の寄付金を充てています。
昭和41年より実施。対象は会員の個人、または会員を中心とした団体としています。
受賞者には、賞状と記念品を贈呈しています。
2.豊かな教育を考える会の企画と運営
松沢研究奨励賞の受賞者を囲んで、教育の課題や諸問題について考え語り合う会を、横国Dayに合わせて実施し、神奈川の教育の充実進展に寄与しています。2019年度には「これからの教師を語る」のテーマでシンポジウムを行いました。
3.学生の就職支援
大学と連携し、就職支援活動として「教員採用試験直前面接対策講座」等を実施しています。(2020年度は中止)
(5) 組織部
県下45支部の現職 (校内)会員と、退職(校外)会員が支部長を中心に支部役員会を構成し、 支部の活動を展開していますが、組織はその活動を支援し組織強化につなげています。
会員名簿を作成し、会員個々の情報を本部に集約し、コンピュータに入力データー化しています。
それにより、全会員と本部との連繋を図っています。
支 部 活 動
県下(東京を含む)45支部の組織による、会員相互の情報交流や親睦を図ることを中心にした支部活動を行っています。
活動の様子は「支部レポート」参照)
同 期 会 活 動
卒業時に同期会を組織、世話役を中心とした情報交流や親睦を図る活動です。
◎未組織の「期」は1日も早い組織化が期待されています。
クリックすると大きく見えます。
YNUプラウド文庫は、社会への貢献が大きいと思われる先達の業績を長く後世に伝え、学生の模範となることを目的に附属図書館内に創設しました。愛蔵書、レリーフ、功績等を図書館内で公開。 横浜国立大学付属図書館 YNUプラウド卒業生文庫
酒 井 恒 氏 経歴と業績 平成25年度友松会推薦
濱 田 隆 志 氏 経歴と業績 平成26年度友松会推薦
小 川 信 夫 氏 経歴と業績 平成27年度友松会推薦
小 島 寅 雄 氏 経歴と業績 平成28年度友松会推薦
内 藤 卯 三 郎 氏 経歴と業績 平成29年度友松会推薦
長 谷 川 善 和 氏 経歴と業績 平成30年度友松会推薦
河 野 隆 氏 経歴と業績 令和元年度友松会推薦
森 久 保 仙 太 郎 氏 経歴と業績 令和2年度友松会推薦
勝 俣 泰 蔵 氏 経歴と業績 令和3年度友松会推薦
朝 倉 彰 氏 経歴と業績 令和4年度友松会推薦
田 近 洵 一 氏 経歴と業績 令和5年度友松会推薦
友松会のあゆみ
明治21年1月、先人各位の絶えざるご精進・ご尽力により、高い理想の灯は「神奈川県友松会」として発足しました。 会名の由来は校庭の松樹を 友とし刻苦勉励する願いからでありました。本県は、全国の先頭を切って、明治9年に師範学校を創立、わが国の教育史に輝かしい足跡を残しています。
明治以来のいわゆる近代日本において、友松会は、神奈川県教育界の一大支柱として地域社会に貢献し、 さらに日本の教育界をリードして百三十余年が経ちました。以来、本会は、幾度か時代の荒波に揉まれ、苦難の道を辿りながらも成長・発展を続け今日に至っています。2020年現在、教育系学部卒業生は3万数千名に達し、会員は約6千3百名が全国で活躍しています。
教育制度の変遷により、校名も神奈川県師範学校、神奈川県女子師範学校、神奈川師範学校、横浜国立大学学芸学部、 同教育学部、同教育人間科学部と改称されてきました。その間も友松会活動は営々と続けられ、その時々の教育課題を真剣に追求し、 会員相互の意見交換の場として意志の疎通を計り、また親睦の場として寄与してきました。
同窓という強い友情の絆で結ばれ、これからも一層の研鑽を積み、同窓会活動を活発にしていきたいと思います。
明治以来のいわゆる近代日本において、友松会は、神奈川県教育界の一大支柱として地域社会に貢献し、 さらに日本の教育界をリードして百三十余年が経ちました。以来、本会は、幾度か時代の荒波に揉まれ、苦難の道を辿りながらも成長・発展を続け今日に至っています。2020年現在、教育系学部卒業生は3万数千名に達し、会員は約6千3百名が全国で活躍しています。
教育制度の変遷により、校名も神奈川県師範学校、神奈川県女子師範学校、神奈川師範学校、横浜国立大学学芸学部、 同教育学部、同教育人間科学部と改称されてきました。その間も友松会活動は営々と続けられ、その時々の教育課題を真剣に追求し、 会員相互の意見交換の場として意志の疎通を計り、また親睦の場として寄与してきました。
同窓という強い友情の絆で結ばれ、これからも一層の研鑽を積み、同窓会活動を活発にしていきたいと思います。
友松会・母校沿革概要
| 1874年(明治7年) | 県内の 4 中学区(横浜、日野、羽鳥、浦賀)に小学校教員養成所を設置 |
| 1875年(明治8年) | 各養成所を第1号~第4号師範学校と改称 |
| 1876年(明治9年) | 第1-4号師範学校を合併し、神奈川県横浜師範学校と改称 後に6月28日を本校「開校記念日」と定める |
| 1879年(明治12年) | 横浜市老松町に移転して神奈川県師範学校と改称 |
| 1887年(明治20年) | 神奈川県尋常師範学校と改称 |
| 1888年(明治21年) | 「友松会」(神奈川県友松会)創立 |
| 1890年(明治23年) | 「友松」発刊1号発行 |
| 1892年(明治25年) | 1890年の出火により鎌倉(雪ノ下)新校舎に移転 |
| 1889年(明治31年) | 神奈川県師範学校と改称 |
| 1907年(明治40年) | 神奈川県女子師範学校設置(岡野町) |
| 1923年(大正12年) | 関東大震災 両校共校舎倒壊 |
| 1925年(大正14年) | 神奈川師範学校本校竣工 |
| 1926年(大正15年) | 神奈川県師範学校創立50周年 |
| 1927年(昭和2年) | 女子師範学校の校舎竣工 |
| 1928年(昭和3年) | 師範学校創立50周年式典 |
| 1932年(昭和7年) | 友松会館落成 |
| 1936年(昭和11年 | 神奈川県師範学校創立60周年 「友松」創立60周年記念誌発刊 |
| 1943年(昭和18年) | 両師範学校を統合し神奈川師範学校男子部・女子部となる |
| 1945年(昭和20年) | 横浜大空襲 女子部校舎一部消失 |
| 1949年(昭和24年) | 横浜国立大学設置(「開学記念日」 6 月1 日) 学芸学部・経済学部・工学部の3 学部で構成 |
| 1951年(昭和26年) | 神奈川師範学校を廃止 |
| 1965年(昭和40年) | 学芸学部鎌倉校舎焼失、横浜市清水ヶ丘に移転 |
| 1966年(昭和41年) | 学芸学部を教育学部に名称変更 |
| 1974年(昭和 49年) | 教育学部常盤台に移転 |
| 1988年(昭和63年) | 友松会創立100周年 「友松」78号 創立100周年記念号発行 |
| 1997年(平成 9 年) | 教育学部を教育人間科学部に改組、 4 課程となる |
| 1998年(平成10年) | 友松会創立110周年 「友松」 88号 創立110周年記念号発行 |
| 2008年(平成20年) | 友松会創立120周年 「友松」 98号 創立120周年記念号発行 |
| 2009年(平成21年) | 横浜国立大学 創立60周年 |
| 2010年(平成 22年) | 「友松」100号 記念号発行 |
| 2017年(平成29年) | 教育人間科学部を教育学部に改称 教職大学院設置 |
| 2018年(平成30年) | 友松会創立130周年 「友松」108号 創立130周年記念号発行 |
明治21年、同窓会の発足に当たり,会則の第3条に次のような記載がある。「本会会員ハ皆曽テ縣校ニアリ 朝夕松樹ヲ友トシ,同窓ニ苦学セルヲ記センガ為,神奈川縣友松会ト名ヅク」