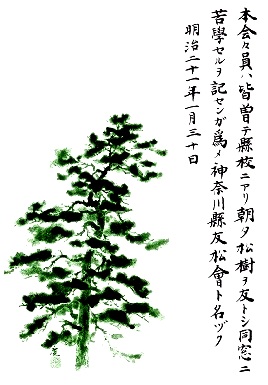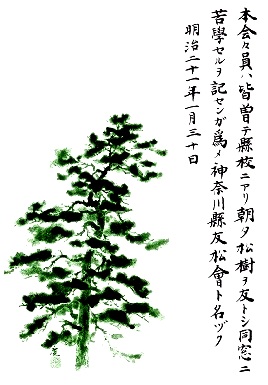友松会について
友松会の明日を「ともに」つくる 会誌「友松」115号 巻頭言
 友松会 会長 藤馬 享 Tohma Susumu
友松会 会長 藤馬 享 Tohma Susumu
このたび、小島勝会長の後任として、会長のご指名を受けました藤馬享でございます。これまで友松会をリードされてきた小島前会長をはじめ、歴代会長の足跡を振り返りながら、微力ではございますが職責を果たしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
今、大学では、学校現場で活躍できる優れた人材を養成しようと、すべての学生に小学校教諭一種免許状の取得を義務づけ、教科専門領域や特別支援教育専門領域などにかかわる一種免許状取得を必須としています。さらに、「学外活動・学外学習」として教育ボランティアに取り組むことを推奨し単位認定していることは特筆すべきことです。
このことを踏まえ、会費納入者の減少という課題とつなげて考えると、「深まろう 高まろう つながる会員 つながる大学」という友松会スローガンを一層意識することが大切です。2015年に始まった10年間の会費一括納入による学生会員制度があります。本年度は、最初の学生会員が会員となる年です。友松会は、ここ数年、学生会員とのつながりを強め、「研究発表会」や「豊かな教育を考える会」への参加を促し教育の魅力に触れる場をつくりました。また、4年生対象の2次試験直前面接講座に加え、2,3年生対象の個人面接講座を新設しました。このように、友松会の存在意義をアピールしていますが、学生会員から会員となる際の働きかけが必要と考えます。また、現役の先生方が会費を納入したいと思うような場を工夫する必要があると思います。
そのためには、会員同士の顔の見える関係づくりのための支部総会や支部活動の推進が第一歩です。そして、現役の先生方が参加してみたいと思う魅力ある取組、教育現場に携わっていない個人会員の方々とのつながりをつくるための工夫、学生会員が会員とつながり教育の魅力を実感する場のさらなる工夫など、友松会の諸活動を一層充実することが『友松会の明日を「ともに」つくる』ことにつながるものと思います。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
このたび、小島勝会長の後任として、会長のご指名を受けました藤馬享でございます。これまで友松会をリードされてきた小島前会長をはじめ、歴代会長の足跡を振り返りながら、微力ではございますが職責を果たしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
今、大学では、学校現場で活躍できる優れた人材を養成しようと、すべての学生に小学校教諭一種免許状の取得を義務づけ、教科専門領域や特別支援教育専門領域などにかかわる一種免許状取得を必須としています。さらに、「学外活動・学外学習」として教育ボランティアに取り組むことを推奨し単位認定していることは特筆すべきことです。
このことを踏まえ、会費納入者の減少という課題とつなげて考えると、「深まろう 高まろう つながる会員 つながる大学」という友松会スローガンを一層意識することが大切です。2015年に始まった10年間の会費一括納入による学生会員制度があります。本年度は、最初の学生会員が会員となる年です。友松会は、ここ数年、学生会員とのつながりを強め、「研究発表会」や「豊かな教育を考える会」への参加を促し教育の魅力に触れる場をつくりました。また、4年生対象の2次試験直前面接講座に加え、2,3年生対象の個人面接講座を新設しました。このように、友松会の存在意義をアピールしていますが、学生会員から会員となる際の働きかけが必要と考えます。また、現役の先生方が会費を納入したいと思うような場を工夫する必要があると思います。
そのためには、会員同士の顔の見える関係づくりのための支部総会や支部活動の推進が第一歩です。そして、現役の先生方が参加してみたいと思う魅力ある取組、教育現場に携わっていない個人会員の方々とのつながりをつくるための工夫、学生会員が会員とつながり教育の魅力を実感する場のさらなる工夫など、友松会の諸活動を一層充実することが『友松会の明日を「ともに」つくる』ことにつながるものと思います。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
前会長より
「みはるかす」に集う
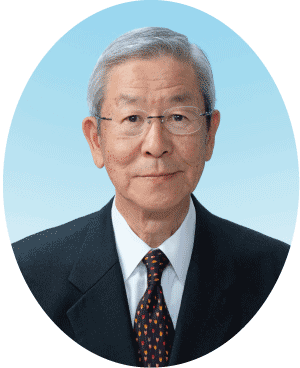
友松会 前会長 小島 勝
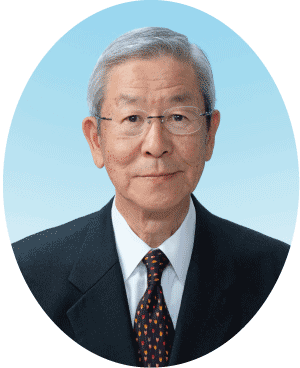
友松会 前会長 小島 勝
学部時代から半世紀以上にわたり歌い継がれてきたこの「みはるかす」を学生はもとより常盤台や清水ヶ丘、鎌倉の卒業生が集う場でこれからも歌い継ぎ、会員同士の絆をより一層深め合えることを願っています。
私が友松会活動に直接携わることになったのは、7年前にある先輩から声を掛けられ断り切れず「イエスとハイ」で引き受けることになってからです。この間に活動を共にした事務局員や役員、常任理事、支部長の方々との関わりの中で気づかせてもらったことがあります。それは、それぞれの役職をたとえ「消極的」に引き受けたとしても自分の立場でやるべきことやできることを精一杯やることで友松会活動は継続し発展してきたのではないかということです。この3年間、役員と専門部員は知恵と労力を惜しみなく出し合って友松会の諸活動に取り組み成果を上げてくれました。また、各支部では支部長や支部役員を中心にコロナ禍により中止になっていた支部総会の復活に努めてくれています。支部総会は、身近な会員同士が集い親睦や資質の向上を図ることで同窓会の良さを実感できる絶好の機会だと思います。
友松会には、ここ10数年来の会費納入率の減少という課題をはじめ、時代の移ろいに伴う新たな課題も出てきています。同窓会活動として10年前や20年前には当たり前であったことが「不適切」とされる時代になっています。このような状況ですが、この度、藤馬新会長をはじめ新役員の皆様に友松会運営の襷を引継いでいただきました。新役員の叡智とエネルギー、そして「みはるかす」に集う皆様のご支援により必ずや諸課題に果敢に取り組んでいただけるものと信じております。
終わりに、この3年間、友松会活動に対してあたたかいご理解と多大のご支援を賜りました会員と関係の皆様に心より感謝申しあげます。
私が友松会活動に直接携わることになったのは、7年前にある先輩から声を掛けられ断り切れず「イエスとハイ」で引き受けることになってからです。この間に活動を共にした事務局員や役員、常任理事、支部長の方々との関わりの中で気づかせてもらったことがあります。それは、それぞれの役職をたとえ「消極的」に引き受けたとしても自分の立場でやるべきことやできることを精一杯やることで友松会活動は継続し発展してきたのではないかということです。この3年間、役員と専門部員は知恵と労力を惜しみなく出し合って友松会の諸活動に取り組み成果を上げてくれました。また、各支部では支部長や支部役員を中心にコロナ禍により中止になっていた支部総会の復活に努めてくれています。支部総会は、身近な会員同士が集い親睦や資質の向上を図ることで同窓会の良さを実感できる絶好の機会だと思います。
友松会には、ここ10数年来の会費納入率の減少という課題をはじめ、時代の移ろいに伴う新たな課題も出てきています。同窓会活動として10年前や20年前には当たり前であったことが「不適切」とされる時代になっています。このような状況ですが、この度、藤馬新会長をはじめ新役員の皆様に友松会運営の襷を引継いでいただきました。新役員の叡智とエネルギー、そして「みはるかす」に集う皆様のご支援により必ずや諸課題に果敢に取り組んでいただけるものと信じております。
終わりに、この3年間、友松会活動に対してあたたかいご理解と多大のご支援を賜りました会員と関係の皆様に心より感謝申しあげます。
赤星直忠―知を継ぐ者
 横浜国立大学学長 梅原 出
横浜国立大学学長 梅原 出
皆さんは、赤星直忠という考古学者の名を聞いたことがあるでしょうか。彼は、神奈川県横須賀市に生まれ、独学で考古学を究め、関東地方の遺跡発掘に生涯を捧げた人物です。
実は、赤星先生は、教育学部の前身である師範学校で学んだ一人でもあります。赤星先生は、学位を持たずとも、自らの探究心のもとに遺跡を調査し、多くの貴重な文化遺産を発掘しました。
――そして、1923年の関東大震災。 この未曾有の災害により横浜の街は壊滅的な被害を受け、多くの文化財が失われました。しかし、震災からの復興のさなか、赤星先生は自ら収集した貴重な考古資料を、彼が学んだ母校である師範学校(現在の横浜国立大学の前身)に寄贈しました。なぜ、震災からの復興のさなかにそのような行動を取ったのでしょうか。
それは、知は、ただ蓄えるものではなく、未来へと継ぐべきものであるという信念があったからにほかならないと、私は考えます。学びとは、個人の成功のためだけにあるのではなく、次世代のために蓄え、伝え、活かされてこそ、その真価を発揮するものです。
令和6年11月、教育学部の多和田雅保教授が中心となり、『自然と関わって生きた人間の歴史-常盤台遺跡と横浜国大キャンパス-』と題したシンポジウムが開催されました。シンポジウムでは、太古から現在に続く「地」と「知」を連綿と受け継いできたことに思いを巡らせつつ、横浜国立大学と地域の未来を展望しました。このシンポジウムで、私は赤星先生の精神にとても感銘を受けました。
赤星先生の精神は、今を生きる私たち、そして、特に、未来の子どもたちを支える教育学部の皆さん・卒業生の皆さんに問いかけています。
――皆さんは、未来に何を残しますか?
これからの教育学部の活躍に期待しています。
 横浜国立大学学長 梅原 出
横浜国立大学学長 梅原 出 皆さんは、赤星直忠という考古学者の名を聞いたことがあるでしょうか。彼は、神奈川県横須賀市に生まれ、独学で考古学を究め、関東地方の遺跡発掘に生涯を捧げた人物です。
実は、赤星先生は、教育学部の前身である師範学校で学んだ一人でもあります。赤星先生は、学位を持たずとも、自らの探究心のもとに遺跡を調査し、多くの貴重な文化遺産を発掘しました。
――そして、1923年の関東大震災。 この未曾有の災害により横浜の街は壊滅的な被害を受け、多くの文化財が失われました。しかし、震災からの復興のさなか、赤星先生は自ら収集した貴重な考古資料を、彼が学んだ母校である師範学校(現在の横浜国立大学の前身)に寄贈しました。なぜ、震災からの復興のさなかにそのような行動を取ったのでしょうか。
それは、知は、ただ蓄えるものではなく、未来へと継ぐべきものであるという信念があったからにほかならないと、私は考えます。学びとは、個人の成功のためだけにあるのではなく、次世代のために蓄え、伝え、活かされてこそ、その真価を発揮するものです。
令和6年11月、教育学部の多和田雅保教授が中心となり、『自然と関わって生きた人間の歴史-常盤台遺跡と横浜国大キャンパス-』と題したシンポジウムが開催されました。シンポジウムでは、太古から現在に続く「地」と「知」を連綿と受け継いできたことに思いを巡らせつつ、横浜国立大学と地域の未来を展望しました。このシンポジウムで、私は赤星先生の精神にとても感銘を受けました。
赤星先生の精神は、今を生きる私たち、そして、特に、未来の子どもたちを支える教育学部の皆さん・卒業生の皆さんに問いかけています。
――皆さんは、未来に何を残しますか?
これからの教育学部の活躍に期待しています。
全国フレンドシップ活動

横浜国立大学 教育学部長・教育研究科長 友松会名誉会長 鈴木 俊彰
全国フレンドシップ活動は、全国の教員養成系大学に在籍する学生たちが一堂に会し、子どもたちとの交流や意見交換を通して互いに学び合う貴重な場です。この活動は、学生たちが教育現場で必要とされるスキルや実践的な指導力を磨きながら、子どもたちに新たな学びや心躍る交流の機会を提供することを目的としています。その結果として、学生たちは教育者として成長し、子どもたちは学校では経験できない特別な体験や学びを得ることができます。
今年度も、令和5年3月に引き続き、教育学部の「わくわくサタデー」と「がやっこ探検隊」に所属する学生有志が実行委員を務め、この活動を運営しました。半年前から準備を進め、令和7年3月8日に横浜国立大学教育学部講義棟を会場に、全国の10大学から約100名の学生たち、約100名の子どもたちが集まりました。参加した学生たちは開催日の4日前から泊まり込みで準備を進め、意見を出し合い、子どもたちとの交流を深めるための企画を練りました。この企画では、子どもたちが楽しめるだけでなく、互いに協力をしながら課題を解決していく仕組みを取り入れたストーリー性のあるゲームを考え、段ボールや画用紙などを使って立体的な教材を製作しました。子どもたちにとってもこのゲームをすることによって、協力やコミュニケーションの重要性を学ぶ素晴らしい機会となりました。また、他校の児童と触れ合うことで、視野を広げ、新しい友人関係を築くきっかけにもなりました。学校では得られない新鮮で刺激的な体験を通じて、主体性や協調性を養い、大きな成長を遂げました。
本活動を実施するにあたり、友松会の皆様には多大なるご支援をいただき、さらに「新春のつどい」の場においても多くの会員の皆様より個人的なご寄付をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。

横浜国立大学 教育学部長・教育研究科長 友松会名誉会長 鈴木 俊彰
全国フレンドシップ活動は、全国の教員養成系大学に在籍する学生たちが一堂に会し、子どもたちとの交流や意見交換を通して互いに学び合う貴重な場です。この活動は、学生たちが教育現場で必要とされるスキルや実践的な指導力を磨きながら、子どもたちに新たな学びや心躍る交流の機会を提供することを目的としています。その結果として、学生たちは教育者として成長し、子どもたちは学校では経験できない特別な体験や学びを得ることができます。
今年度も、令和5年3月に引き続き、教育学部の「わくわくサタデー」と「がやっこ探検隊」に所属する学生有志が実行委員を務め、この活動を運営しました。半年前から準備を進め、令和7年3月8日に横浜国立大学教育学部講義棟を会場に、全国の10大学から約100名の学生たち、約100名の子どもたちが集まりました。参加した学生たちは開催日の4日前から泊まり込みで準備を進め、意見を出し合い、子どもたちとの交流を深めるための企画を練りました。この企画では、子どもたちが楽しめるだけでなく、互いに協力をしながら課題を解決していく仕組みを取り入れたストーリー性のあるゲームを考え、段ボールや画用紙などを使って立体的な教材を製作しました。子どもたちにとってもこのゲームをすることによって、協力やコミュニケーションの重要性を学ぶ素晴らしい機会となりました。また、他校の児童と触れ合うことで、視野を広げ、新しい友人関係を築くきっかけにもなりました。学校では得られない新鮮で刺激的な体験を通じて、主体性や協調性を養い、大きな成長を遂げました。
本活動を実施するにあたり、友松会の皆様には多大なるご支援をいただき、さらに「新春のつどい」の場においても多くの会員の皆様より個人的なご寄付をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。
本 部 活 動
各部が分担した業務を中心に活動し、(本部活動として)協力して事業を推進しています。
(1) 総務部
友松会百三十余年の灯を継続、発展させるためにも会員相互の意識の昂揚と結束が求められています。
1.諸会議の企画運営と効率化
2.母校との連携と情報入手
3.各部会相互の連絡調整 新春のつどい等、親睦の会の企画運営
4.活動の基本になる会則、規則、細則等の見直し
など会の円滑な運営に心がけ、活性化を計っています。
(2) 経理部
主たる分担業務は、本部の経理事務、年度予算・決算を担当しています。
そのため事務局と常時連携を図り、会の運営の円滑化に務めています。
部会で課題の検討を図るほか、会費の納入状況の確認ならびに支出状況の把握等、会計整理の活動を行っています。
特に、年度予算案の立案と決算に関する活動は、会の活性化や発展を図る意味でも重要な会務と考えています。
(3) 弘報部
○会誌「友松」の発行
主な業務として、友松会会誌「友松」の編集・発行・発送を行っています。
友松会会誌「友松」はA4版で、毎年6月に発行を予定しています。
○会誌の主な内容
大学教授の寄稿、会員の教育論考、人生についての考え方等を軸に構成しています。
また、「豊かな教育を考える会」報告、「松沢研究奨励賞受賞者」研究論文、 同期会報告、支部だより等の会員相互の情報、 総会、新春のつどいの報告、各年度の会務会計報告、会員の消息、組織名簿等を掲載し、豊かな会誌にするよう努力しています。
(4) 研修部
会員の研修を深めるため、次の業務を中心に活動しています。
1.松沢研究奨励賞受賞者の選考
研究奨励基金は、本会の元顧問・ 相沢義雄氏 (大正13年卒)が、叔父の松沢高次郎氏(明治13年卒)の遺志を顕彰するために寄付された基金とし、吉田太郎氏、水戸部正男氏、大浦美代氏の寄付金を充てています。
昭和41年より実施。対象は会員の個人、または会員を中心とした団体としています。
受賞者には、賞状と記念品を贈呈しています。
2.豊かな教育を考える会の企画と運営
教育の課題や諸問題について考え語り合う会を、横国Dayに合わせて実施し、神奈川の教育の充実進展に寄与しています。2024年度には「目の前の子どもがすこやかに育つために 今 私たちにできること」をテーマにしてシンポジウムを行いました。
3.学生の就職支援
大学と連携し、就職支援活動として「2次試験個人面接対策講座」等を実施しています。
(5) 組織部
県下44支部の現職 (校内)会員と、退職(校外)会員が支部長を中心に支部役員会を構成し、 支部の活動を展開していますが、組織はその活動を支援し組織強化につなげています。
会員名簿を作成し、会員個々の情報を本部に集約し、データー化しています。
それにより、全会員と本部との連携を図っています。
支 部 活 動
県下(東京を含む)44支部の組織による、会員相互の情報交流や親睦を図ることを中心にした支部活動を行っています。
活動の様子は「支部だより」を参照してください。
同 期 会 活 動
卒業時に同期会を組織、世話役を中心とした情報交流や親睦を図る活動です。
◎未組織の「期」は1日も早い組織化が期待されています。
事 務 局
各部、各支部、大学、学生及び横国大他同窓会と連携を取り、それぞれの組織や個人が「つながる」ようにサポートしています。
会員名簿の集約、整理及び会誌「友松」の発送をしています。
予算案に沿って会費を適切に執行し、会の円滑な運営に寄与しています。
同窓会案内等の印刷物の編集をしています。
HPの充実を図り、行事・会議日程、活動報告、友松だより等を掲載し、適宜更新に努めながら会の概要及び各種情報提供をしています。
各部が分担した業務を中心に活動し、(本部活動として)協力して事業を推進しています。
(1) 総務部
友松会百三十余年の灯を継続、発展させるためにも会員相互の意識の昂揚と結束が求められています。
1.諸会議の企画運営と効率化
2.母校との連携と情報入手
3.各部会相互の連絡調整 新春のつどい等、親睦の会の企画運営
4.活動の基本になる会則、規則、細則等の見直し
など会の円滑な運営に心がけ、活性化を計っています。
(2) 経理部
主たる分担業務は、本部の経理事務、年度予算・決算を担当しています。
そのため事務局と常時連携を図り、会の運営の円滑化に務めています。
部会で課題の検討を図るほか、会費の納入状況の確認ならびに支出状況の把握等、会計整理の活動を行っています。
特に、年度予算案の立案と決算に関する活動は、会の活性化や発展を図る意味でも重要な会務と考えています。
(3) 弘報部
○会誌「友松」の発行
主な業務として、友松会会誌「友松」の編集・発行・発送を行っています。
友松会会誌「友松」はA4版で、毎年6月に発行を予定しています。
○会誌の主な内容
大学教授の寄稿、会員の教育論考、人生についての考え方等を軸に構成しています。
また、「豊かな教育を考える会」報告、「松沢研究奨励賞受賞者」研究論文、 同期会報告、支部だより等の会員相互の情報、 総会、新春のつどいの報告、各年度の会務会計報告、会員の消息、組織名簿等を掲載し、豊かな会誌にするよう努力しています。
(4) 研修部
会員の研修を深めるため、次の業務を中心に活動しています。
1.松沢研究奨励賞受賞者の選考
研究奨励基金は、本会の元顧問・ 相沢義雄氏 (大正13年卒)が、叔父の松沢高次郎氏(明治13年卒)の遺志を顕彰するために寄付された基金とし、吉田太郎氏、水戸部正男氏、大浦美代氏の寄付金を充てています。
昭和41年より実施。対象は会員の個人、または会員を中心とした団体としています。
受賞者には、賞状と記念品を贈呈しています。
2.豊かな教育を考える会の企画と運営
教育の課題や諸問題について考え語り合う会を、横国Dayに合わせて実施し、神奈川の教育の充実進展に寄与しています。2024年度には「目の前の子どもがすこやかに育つために 今 私たちにできること」をテーマにしてシンポジウムを行いました。
3.学生の就職支援
大学と連携し、就職支援活動として「2次試験個人面接対策講座」等を実施しています。
(5) 組織部
県下44支部の現職 (校内)会員と、退職(校外)会員が支部長を中心に支部役員会を構成し、 支部の活動を展開していますが、組織はその活動を支援し組織強化につなげています。
会員名簿を作成し、会員個々の情報を本部に集約し、データー化しています。
それにより、全会員と本部との連携を図っています。
支 部 活 動
県下(東京を含む)44支部の組織による、会員相互の情報交流や親睦を図ることを中心にした支部活動を行っています。
活動の様子は「支部だより」を参照してください。
同 期 会 活 動
卒業時に同期会を組織、世話役を中心とした情報交流や親睦を図る活動です。
◎未組織の「期」は1日も早い組織化が期待されています。
事 務 局
各部、各支部、大学、学生及び横国大他同窓会と連携を取り、それぞれの組織や個人が「つながる」ようにサポートしています。
会員名簿の集約、整理及び会誌「友松」の発送をしています。
予算案に沿って会費を適切に執行し、会の円滑な運営に寄与しています。
同窓会案内等の印刷物の編集をしています。
HPの充実を図り、行事・会議日程、活動報告、友松だより等を掲載し、適宜更新に努めながら会の概要及び各種情報提供をしています。
クリックすると大きく見えます。
YNUプラウド文庫は、社会への貢献が大きいと思われる先達の業績を長く後世に伝え、学生の模範となることを目的に附属図書館内に創設しました。愛蔵書、レリーフ、功績等を図書館内で公開。 横浜国立大学付属図書館 YNUプラウド卒業生文庫
酒 井 恒 氏 経歴と業績 平成25年度友松会推薦
濱 田 隆 志 氏 経歴と業績 平成26年度友松会推薦
小 川 信 夫 氏 経歴と業績 平成27年度友松会推薦
小 島 寅 雄 氏 経歴と業績 平成28年度友松会推薦
内 藤 卯 三 郎 氏 経歴と業績 平成29年度友松会推薦
長 谷 川 善 和 氏 経歴と業績 平成30年度友松会推薦
河 野 隆 氏 経歴と業績 令和元年度友松会推薦
森 久 保 仙 太 郎 氏 経歴と業績 令和2年度友松会推薦
勝 俣 泰 蔵 氏 経歴と業績 令和3年度友松会推薦
朝 倉 彰 氏 経歴と業績 令和4年度友松会推薦
田 近 洵 一 氏 経歴と業績 令和5年度友松会推薦
宮 田 進 氏 経歴と業績 令和6年度友松会推薦
友松会のあゆみ
1888年(明治21年)1月30日、先人各位の絶えざるご精進・ご尽力により、高い理想の灯は「神奈川県友松会」として発足しました。 会名の由来は校庭の松樹を 友とし刻苦勉励する願いからでありました。本県は、全国の先頭を切って、明治9年に師範学校を創立、わが国の教育史に輝かしい足跡を残しています。
明治以来のいわゆる近代日本において、友松会は、神奈川県教育界の一大支柱として地域社会に貢献し、 さらに日本の教育界をリードして百三十余年が経ちました。以来、本会は、幾度か時代の荒波に揉まれ、苦難の道を辿りながらも成長・発展を続け今日に至っています。2020年現在、教育系学部卒業生は3万数千名に達し、会員は約6千3百名が全国で活躍しています。
教育制度の変遷により、校名も神奈川県師範学校、神奈川県女子師範学校、神奈川師範学校、横浜国立大学学芸学部、 同教育学部、同教育人間科学部と改称されてきました。その間も友松会活動は営々と続けられ、その時々の教育課題を真剣に追求し、 会員相互の意見交換の場として意志の疎通を計り、また親睦の場として寄与してきました。
同窓という強い友情の絆で結ばれ、これからも一層の研鑽を積み、同窓会活動を活発にしていきたいと思います。
明治以来のいわゆる近代日本において、友松会は、神奈川県教育界の一大支柱として地域社会に貢献し、 さらに日本の教育界をリードして百三十余年が経ちました。以来、本会は、幾度か時代の荒波に揉まれ、苦難の道を辿りながらも成長・発展を続け今日に至っています。2020年現在、教育系学部卒業生は3万数千名に達し、会員は約6千3百名が全国で活躍しています。
教育制度の変遷により、校名も神奈川県師範学校、神奈川県女子師範学校、神奈川師範学校、横浜国立大学学芸学部、 同教育学部、同教育人間科学部と改称されてきました。その間も友松会活動は営々と続けられ、その時々の教育課題を真剣に追求し、 会員相互の意見交換の場として意志の疎通を計り、また親睦の場として寄与してきました。
同窓という強い友情の絆で結ばれ、これからも一層の研鑽を積み、同窓会活動を活発にしていきたいと思います。
友松会・母校沿革概要
| 1874年(明治7年) | 県内の 4 中学区(横浜、日野、羽鳥、浦賀)に小学校教員養成所を設置 |
| 1875年(明治8年) | 各養成所を第1号~第4号師範学校と改称 |
| 1876年(明治9年) | 第1-4号師範学校を合併し、神奈川県横浜師範学校と改称 後に6月28日を本校「開校記念日」と定める |
| 1879年(明治12年) | 横浜市老松町に移転して神奈川県師範学校と改称 |
| 1887年(明治20年) | 神奈川県尋常師範学校と改称 |
| 1888年(明治21年) | 「友松会」(神奈川県友松会)創立 1月30日 |
| 1890年(明治23年) | 「友松」発刊1号発行 |
| 1892年(明治25年) | 1890年の出火により鎌倉(雪ノ下)新校舎に移転 |
| 1889年(明治31年) | 神奈川県師範学校と改称 |
| 1907年(明治40年) | 神奈川県女子師範学校設置(岡野町) |
| 1923年(大正12年) | 関東大震災 両校共校舎倒壊 |
| 1925年(大正14年) | 神奈川師範学校本校竣工 |
| 1926年(大正15年) | 神奈川県師範学校創立50周年 |
| 1927年(昭和2年) | 女子師範学校の校舎竣工 |
| 1928年(昭和3年) | 師範学校創立50周年式典 |
| 1932年(昭和7年) | 友松会館落成 |
| 1936年(昭和11年 | 神奈川県師範学校創立60周年 「友松」創立60周年記念誌発刊 |
| 1943年(昭和18年) | 両師範学校を統合し神奈川師範学校男子部・女子部となる |
| 1945年(昭和20年) | 横浜大空襲 女子部校舎一部消失 |
| 1949年(昭和24年) | 横浜国立大学設置(「開学記念日」 6 月1 日) 学芸学部・経済学部・工学部の3 学部で構成 |
| 1951年(昭和26年) | 神奈川師範学校を廃止 |
| 1965年(昭和40年) | 学芸学部鎌倉校舎焼失、横浜市清水ヶ丘に移転 |
| 1966年(昭和41年) | 学芸学部を教育学部に名称変更 |
| 1974年(昭和 49年) | 教育学部常盤台に移転 |
| 1988年(昭和63年) | 友松会創立100周年 「友松」78号 創立100周年記念号発行 |
| 1997年(平成 9 年) | 教育学部を教育人間科学部に改組、 4 課程となる |
| 1998年(平成10年) | 友松会創立110周年 「友松」 88号 創立110周年記念号発行 |
| 2008年(平成20年) | 友松会創立120周年 「友松」 98号 創立120周年記念号発行 |
| 2009年(平成21年) | 横浜国立大学 創立60周年 |
| 2010年(平成 22年) | 「友松」100号 記念号発行 |
| 2017年(平成29年) | 教育人間科学部を教育学部に改称 教職大学院設置 |
| 2018年(平成30年) | 友松会創立130周年 「友松」108号 創立130周年記念号発行 |
| 2024年(令和6年) | 横浜国立大学創基150周年 開学75周年 「みはるかす」歌碑 横浜国立大学内に設置 |
明治21年、同窓会の発足に当たり,会則の第3条に次のような記載がある。「本会会員ハ皆曽テ縣校ニアリ 朝夕松樹ヲ友トシ,同窓ニ苦学セルヲ記センガ為,神奈川縣友松会ト名ヅク」